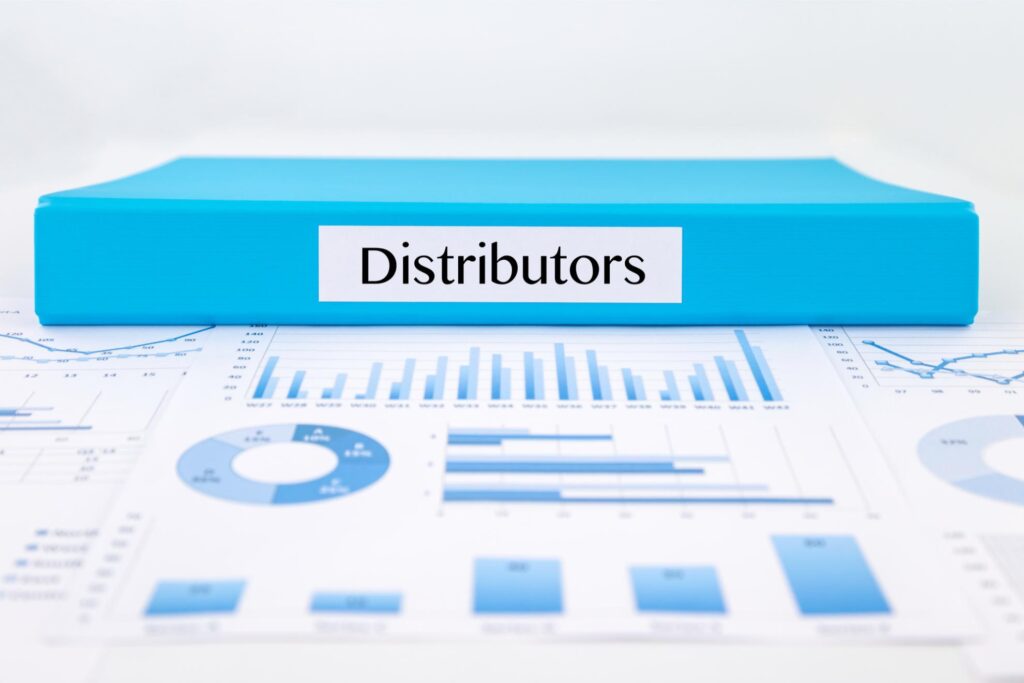〜『Music Ally Japan Pro Meetup Vol.6』レポート〜
2025年8月、東京・渋谷のレコチョク本社で「Music Ally Japan Pro ミートアップ(MAJ Meetup)」の第6回が開催された。
「Music Ally Japan Pro」は、音楽ビジネスに携わる人と組織が、実践的なデジタルマーケティングに関わるナレッジを拡大し、個人のスキルや企業の強みを最大化することを支援するワンストップサービス。その会員向けネットワーキングイベントとして定期的に行われているのが「MAJ Meetup」だ。
今回のテーマは「楽曲の発見性を高める“ベストな納品”とは?〜DSPの最新動向から分析する、メタデータ整備の最前線〜」。
ストリーミングを軸にした音楽ビジネスが拡大し、現在、配信オペレーションにおけるメタデータ整備は欠かせない業務となっている。しかし、DSPの要件や基準は目まぐるしく変化し続けており、「また仕様が変わったのか」と、ため息をついた経験を持つ方も多いのではないだろうか。
Meetupでは、こうした課題感を背景に、レコチョク 折戸彰氏と、SPACE SHOWER FUGA 山岸毅氏が登壇。自らの経験をもとに、率直な意見を交わした。
本記事では、そのMeetupの模様をレポートする。
「良い納品」とは何か
音楽配信は今や業界全体を支える基盤となり、その基準や仕様も日々アップデートされている。
「納品」という業務に限ってみても、かつてはシステム上のエラーがなく、DSPから滞りなく配信できることが「良い納品」の基準だった。
だが今は、リスナーに見つけてもらえるかどうか、つまり「発見性」が問われる時代になっている。まずは、そうした変化の中で現場が直面している課題や対応について、両氏に語ってもらった。

納品の質を左右する「コントリビューター※1」
「良い納品」を考える上で欠かせないのが「コントリビューター」だ。
従来は「裏方」のクレジットとして扱われてきたが、近年はDSPにおける表示や検索性に直結するメタデータ項目として重要性が高まってきた。今や配信業務においては、単なる付随情報ではなく、楽曲の発見性を左右する中核的なデータと位置付けられている。
両氏は「エラーがないのは大前提」とした上で、コントリビューターをめぐる現状をこう語る。
折戸:「(Apple等は以前からあったが)最近では、Amazonも納品データの品質にスコアを付ける仕組みが導入されています。私たちは、最低限そこを意識しないといけない。そして、最近特にDSPからリクエストが強くなっているのがコントリビューター。楽曲が発見されるかどうかという点で、コントリビューターの拡充も重要になってきています」
山岸:「おっしゃる通りで、Appleなどはコントリビューター情報をより正確に、より多く網羅しようとしています。肌感覚で言うと、いわゆる洋楽と言われる海外アーティストの楽曲だったり、ジャズだったり、参加人数が多いジャンルでは可視化が一気に進んでいますね。一方で、ほとんど入っていないケースもまだ多い。この差は顕著に表れています」
膨大な情報との格闘
コントリビューター情報は、もはや裏方のクレジットにとどまらず、サービス設計や産業の仕組みにまで影響を及ぼし始めている。ユーザーがどのように音楽と出会い、どこまで制作者の足跡をたどれるのか。その視点からも、各社の取り組みが動き出している。
折戸:「Apple Classicalのように、コントリビューターをたどって作品を楽しむサービスも登場しています。今はまだAppleではきちんと表示される程度にとどまっていますが、コントリビューターの整備が必須だという意識は、配信の本質にもつながっていくと思います」
山岸:「弊社でも昨年あたりから、ディレクターやプロデューサーといったロール(役割)の部分、そして、膨大な数の楽器情報の部分、トータルで数百のコントリビューター情報を用意して、メタデータ上、ダッシュボード上で対応できる形を整えています。Appleはすでにそうした情報がきちんと表示されていて、今後は検索もできるようになる。ユーザーにとってはすごく楽しい状況になりそうだと思っています。ただ一方で、コントリビューターが正しく実装されていないサービスもまだ多いのが現状です。そこに向けて、最適な形を探りながら、ディストリビューターとして環境を整えていこうとしています。そして、その背景や意味合いをクライアントの皆さんと共有していくことも大事だと思っています」
折戸:「ただ、実際にコントリビューターを入れるのは大変なんですよね。“管理できていません”という会社も多いです。宣伝みたいになりますけど、レコチョクでも『FLAGGLE』というソリューションがありまして、コントリビューター情報を埋められる仕組みを研究・検討しています。よかったら相談いただければと思います」
入力の手間を思うと気が遠くなるが、その一つひとつが楽曲の発見性に直結するという事実を、日々体感している方も多いだろう。
では、実際に楽曲はどのように「発見」され、再生へと結びついていくのか。
議論は、再生数を左右する仕組みと、メタデータの関係に移っていく。

メタデータが動かす楽曲の「数字」
音楽配信における「発見性」は、もはや偶然に左右されるものではない。
ジャンルの付け方や言語の扱いなど、細部まで整え表記を揃えることで、楽曲発見への道筋は意図して設計できるようになってきている。
発見につながる表記の重要性
メタデータ上のわずかな表記の揺れが致命的な結果を招くこともある。
同じ楽曲なのに別作品として扱われてしまい、メタデータが分断される。結果として、再生や発見の機会を失ってしまうケースは決して少なくない。
山岸:「一番シンプルな例で言うと、アーティスト名や曲名の表記の揺れですね。これがあると、同じ楽曲でも別作品に収録されたときに統一されず、結果としてリスティングが崩れてしまう。アーティストページが分かれて機会損失になるケースもあります。ISNI※2みたいな仕組みで統一されることに期待はありますが、まだどのサービスでも網羅的に使える状態ではない。だから現場としては、まず表記の揺れをきちんと整えることが欠かせないと思います」
折戸:「再生数への影響という観点から考えると、一番大きいのはやっぱりプレイリストに入るかどうかですよね。今は再生の大半がプレイリスト経由だと言われていますから。そのときにメタデータの観点で考えると、どうやったらプレイリストに入れるのかがポイントになる。最近だとSpotifyがAIプレイリストをベータ版で始めています。プロンプトを入力したときに曲が引っ張られるかどうかは、ピッチの仕方もそうですが、メタデータの網羅性がどれだけあるか、そしてそのプロンプトに対応できる情報を入れられるかどうかにかかっている。正直、そのやり方に“これが正解”というものはありません。ただ今後は、AIが作るプレイリストに対応できるように意識していく必要があると思います」
メタデータの整備は、もはや単なる入力作業ではなく、再生数やリスナーとの接点を左右する“戦略的要素”として取り組むべき課題だということがわかるだろう。

配信管理のボトルネック
次に浮かび上がったのは、データ整備だけでは解決できない「体制と運用」の問題だった。
新しい仕組みを導入しても、情報が一部に偏ったり部署間で断絶があれば、期待した効果は得られない。こうした課題はどの業務にも起こり得るが、配信の現場では特に深刻さが増す。

属人化と分断が生む停滞
「この人が休めば止まる」「部署間で情報がつながらない」──そんな属人化や縦割りの弊害は、配信業務を停滞させる大きな要因だ。その解決策について2人はこう語る。
折戸:「実際のところ、まだデータベースを管理できていない権利者の方も多いんです。誰か一人のPCにメタデータや素材が全部入っていて、そこから動かせないケースも珍しくない。新しいデータベースを導入して“これで効率化できる”と思っても、いざデータを入れる段階になるとリソースが足りない、必要な情報が見つからない、結局管理されていなかった――そういう壁にぶつかるんです。だからこそ、そこを具体的に寄り添って一緒に実行できるパートナーと組むことが大事だと思います」
山岸:「本当におっしゃる通りで、僕らもこういう場で情報を得ながら、皆さんのニーズを踏まえて取り組んでいます。ポイントは、配信のメタ情報だけに限らないということなんですよね。管理や運用全体の話になる。外部ツールを使う場合も、そこでまた別に登録が必要になると、単純に運用負荷が増えてしまう。だからこそ、どう連携させるかが大事だと思います。それはさっきのコントリビューターの話にもつながります。配信チームが持っている情報と、制作やプロモーション、ピッチを担当するチームが持っている情報がバラバラだと、どうしてもズレが生まれる。そのズレを外部ツールで補えるなら、配信にとって大きなプラスになるはずです。情報がきちんとつながれば、ピッチもうまくいき、プレイリストにもつながっていく。だから僕らも、そうした連携をすごく重視しています」
仕様の違いが突きつける現実
外部ツールの活用は「自社の状態や課題に合っているかどうか」を正しく見極めることが重要。コントリビューターについて言えば、実際にはAppleのように対応が進んでいる事例もあれば、他のDSPではメタデータ整備の特徴や進み具合に差がある。現場ではその違いをどう捉えているのだろうか。
折戸:「各社ごとにメタデータ整備の大きな特徴があるわけではないと思います。ただ、さっきから話に出ているコントリビューターについては、実際に触れている方ならご存じの通り、Appleが求める仕様と、DDEX※3で定義されているもの、さらにYouTubeが受け入れるものがそれぞれ違います。だから、送ったのに期待通りに反映されないこともあるんです。たとえばYouTubeに入れると“Unknown”と表示されてしまうケースもあります。結局、細かく入力すれば必ずうまくいくというわけではなくて、実際には手探りや情報共有をしながら対応しているのが現状です。やりたいことはあっても、その通りの結果になるかどうかは課題ですね」
コントリビューター情報はサービスごとに仕様が異なり、思った通りに反映されない難しさがある。現場では試行錯誤しながら対応を重ねているのが実情だ。
この課題に対し、山岸氏は「表示できるサービスそのものがまだ限られている」と前置きしつつ、プラットフォーム側の取り組みについて語った。
山岸:「私たちとしては、そうしたニーズに幅を持って対応していくことが大事だと思っています。DSP側のニーズもそうですし、その先にあるユーザーエクスペリエンス的なものをどう高められるかという視点も欠かせません。プラットフォームとしては、できるだけ幅広く情報を受け入れられる体制を整えているところです。個人的には、コントリビューター情報が今後もっと充実していくのは喜ばしい進化だと思います。CDのブックレットには当たり前のように載っていた情報ですし、ユーザーにとっては調べられるだけでも価値がありますからね」
体制やデータ仕様の違いといった壁に直面しながらも、現場は試行錯誤を重ねている。だが課題は国内対応にとどまらない。次に議論が向かったのは、日本から海外へ音楽を届ける際のハードルだった。
海外配信に向けての努力
日本から海外市場に音楽を届ける際、記号やカタカナ表記など、国内では自然に通じるデータが、そのままでは処理されないケースもある。グローバル基準に寄せながら、日本独自の表現をどう届けるのか――ここからは海外配信ならではの課題が語られた。

立ちはだかる日本語の壁
海外展開の話になると、真っ先に浮かぶのが「言葉」の問題。ローマ字や記号の扱いだけではない。私たちが当たり前に使っている分類や言い回しが、そもそも海外には存在しないこともある。
山岸:「正直いま、国内と海外を分けて考える感覚はあまりないんですが、ジャンルの設定については違いが出ています。たとえば僕らは普段“J-ROCK”と普通に言いますよね。メディアでもよく使われる言葉です。でもグローバルの配信プラットフォームに“J-ROCK”というジャンルがあるかというと、当然ない。だからジャンルをどう設定するか、どう落とし込むかはディストリビューターによっても違いますし、DSPによっても扱いが異なります。その違いをきちんと理解したうえで、クライアントの皆さんに説明することは日常的にやっていますね」
折戸:「おっしゃる通りだと思います。そのうえで、皆さんが一番苦労されているのは“日本語の難しさ”じゃないでしょうか。課題として、ローマ字表記をどうするかとか、全部を埋めないと海外には出せない、出しても発見されにくい――そういう日本語ならではの壁があるんです」
AIの限界を超えるために
AIによる補完は進んでいるものの、日本語の壁は依然として高い。現場では、人間の判断を軸に、日本語の壁を乗り越えるための努力が続けられている。
折戸:「AIの精度は上がってきているものの、まだ実用レベルとは言えない状況です。一方で、コントリビューターについてもまだ網羅されていません。例えば三味線や太鼓といった日本特有の楽器が登録されていないこともある。そういうときはDSPに直接働きかけて追加してもらうこともできます。そこは遠慮せずにコミュニケーションを取るのが大事だと思っています」
グローバルな配信環境に合わせて整備を進めようとしても、日本独自の文化や言語には常に「翻訳不能」の領域が残る。その隔たりを埋めるには、やはり人が動き、声を届けることが欠かせないようだ。
折戸:「日本語の場合、タイトルに記号が入っていたり、音読み・訓読みの違いで意図通りに読まれなかったりすることがあります。以前は『花より男子』の“男子”が“だんご”と読んでもらえないというケースもありました。最近はかなり改善されていますが、それでも日本語ならではの難しさは残っています。やはり一つの正解をAIに任せるのは難しいので、サポートツールとして補助的に使うのが現実的だと思います」
国内では当たり前の表記や分類も、海外では処理されず発見性を損なう。結局のところ、万能の仕組みはなく、現場は手探りの調整を積み重ねているのが実情だ。だからこそ求められるのは、データの整備そのものよりも、それをどう支え、どう運用していくかという視点なのである。
配信を進化させる支援のカタチ
データ整備、体制運用、そして海外対応や言語の壁――。
今回のMeetupを通じて見えてきたのは、配信現場だけでは抱えきれないほどの多くの課題だった。
それらを乗り越えていくために両氏が提示したのは、これからの配信をさらに進化させる「新しい支援のカタチ」だった。

自分たちで共に舵を取れる現場づくり
かつて音楽配信の現場では、外部に丸投げに近い形で進められることも多く、誰がどう手配したのか分からない、資料も残っていない――そんなケースが少なくなかったのだという。
山岸:「振り返ると最初は本当にシンプルなものでした。配信が始まった当初は社内で関わる人もごく限られていて、昔の音源やレーベルコピー、アセットをまとめて外部に渡して“お願いします”という形で始まっていたんです」
そんな時代の教訓からか、山岸氏は「丸投げ」ではなく協働の重要性を強調する。
山岸:「配信を完全に委ねるのではなく、自分たちで状況を把握し、選択できる環境を持つこと。そのための情報共有や仕組みづくりが不可欠だと思います。特にインディペンデントシーンでは、自分たちの手で舵を取ることが重要だと思います」
情報を一つに束ねるための環境づくり
バラバラに動く部署や担当を、どうすれば同じ方向に向かわせられるのか。
折戸氏は、実際の現場から聞こえてくる声を踏まえて、解決の糸口を示した。
折戸:「いろいろなレーベルさんと話していると、業務が縦割りになっていて、情報が伝言ゲームのようにずれてしまう。アウトプットとインプットが噛み合わない、という声をよく耳にします。これを解消するには、共通のデータベースやアナリティクスを活用して、配信担当だけでなく制作も同じ情報を見ながら作業できる環境が理想だと思います」
現状では手作業が多く、新しいサービスや資産活用の機会が来ても即応できないことが珍しくない。せっかくのチャンスが、煩雑な運用フローや情報の断絶によって活かしきれないのが実情だ。
折戸:「さらに、配信担当はDSPごとの仕様変更や環境のアップデート、メタデータ要件の変化に日々追われています。その結果、特定の人に依存する属人的な体制になりがちです。だからこそオペレーションを支える支援――ナレッジの提供やコンサル、あるいは外部のサポート体制が重要で、課題解決のカギになると思っています」
配信の未来を拓く「プラスワンの手立て」
現場の課題は属人化や縦割りにとどまらない。制作から配信、プロモーションへと続く「情報の流れ」全体が問われている。工程のどこかで分断が生まれれば、データを整えても動きは止まってしまう。
だからこそ求められるのは、単なる作業支援ではない。ライツホルダーとディストリビューターがスムーズに連携し、戦略レベルまで視野に入れられる体制だ。2人は、その実現に向けた「プラスワンの手立て」を明かした。
折戸:「レーベルやライツホルダーの方々が本当に評価されるべき業務と、実務的に配信を回す作業は切り分けて考えるべきだと思います。その上で、どこにリソースを割くのかを見直し、弊社の『FLAGGLE』のような外部のツールを活用することで、本来やるべき仕事に集中できる環境を整えることが大事だと思います」
山岸:「社内の体制についても、従来の配信チームという枠を超えて、もっと有機的につながる形になればいいと思います。組織改善だけではなく、可視化された共有ツールが使えるのが理想的ですよね。立場の違う人たちが、同じ情報に同時にアクセスできる環境が必要だと思います」
終わりに
Meetupを通じて浮かび上がったのは、複雑化する配信オペレーションをどう支えるか、という根本的な問いだった。
とりわけ未配信楽曲をなくし、すべてを正しく届けること――折戸氏が語ったように、これをクリアしない限り次の戦略には進めない。
その土台を整えてこそ、発見性を高めるマーケティングや新しい配信戦略に本気で取り組める。
レーベルやライツホルダーが本来の役割に集中できる環境づくりに関心をお持ちなら、レコチョクの「FLAGGLE」といった外部のソリューションツールの導入を、視野に入れてみるのもいいかもしれない。

※1 コントリビューター(Contributor):楽曲制作に関わったすべての人を指す。作詞家・作曲家・編曲家・演奏者・プロデューサー・エンジニアなどが含まれ、作品の完成に貢献した全員が対象。
※2 ISNI(International Standard Name Identifier):作家・演奏家・編曲家などの識別子を世界共通で割り当て、重複や誤記を防止。
※3 DDEX(Digital Data Exchange):配信メタデータの国際標準。コントリビューター情報も細かく定義。